ヒマラヤ山脈に位置する世界最高峰・エベレスト。標高8848メートル、世界中の登山家たちを魅了するその山頂は、生と死が隣り合わせの地球上で最も危険な場所でもある。その山に、「単独・無酸素」という過酷な条件で挑み続ける男がいる。登山家・栗城史多だ。しかも栗城は、「冒険を共有」するため、数キロの重さになるの映像機材を持ってその山に挑む。中継された映像には、エベレストの美しさと厳しさ、栗城たちの苦悩と葛藤が映し出される。2012年の挑戦で、栗城は凍傷により手指9本を失った。それでも栗城はエベレストに挑み続ける。なぜそこまでして「挑戦」を続けるのか。山で感じる「苦悩」や死に対する「恐怖」とどう向き合っているのか。その思いに迫る。
登頂する欲望に打ち克ち、生きて帰る
2015年9月。栗城はこの秋唯一の登山者として、2012年の挑戦で手指9本を失って以来初となる、5度目のエベレストに挑んだ。登頂こそ果たせなかったものの、栗城は自身の最高到達点を更新し、生きて帰ってきた。
「はじめて良い登山ができました。5回目にして。山の大先輩に『山を見るんじゃなくて、自分を見ろ』と言われていたんですが、やっとその意味が理解できました。今回頂上には行けなかったけれど、山を楽しむことができた。楽しいといっても、辛いことばかりなんですけど、自分というものにはじめて向き合えた登山でした」
5度目のエベレストをそう振り返る栗城の表情は、その言葉通り清々しい。
「必ず登頂するという欲望に打ち克てよ」
5度目のエベレストに挑戦する直前に、85歳の大師匠にいわれた言葉だ。酸素が薄く、眠れない日が続くと登りたいという気持ちが狂気に変わることもある。栗城は今回のエベレストでは「静寂」を意識した。熱すぎず冷めすぎず、一定の精神状態を保つ。山頂に近くなれば、ただ立っているだけでも脈は110を超え、焦ったり気持ちが高ぶったりすればさらに脈が早くなりエネルギーも消費する。思考が生死を左右するのだ。死に対する恐怖を忘れ、登る欲望が高まれば、生きることができない世界。エベレストの頂上に辿り着いたとしても、生きて帰ってこなければ意味がない。疲れと達成感からエベレストでは下山時に命を落とす人が多いという。
「生きていれば必ずまた挑戦できる」
栗城は山の先輩がくれたこの言葉を胸に、近く見えたというエベレストの頂上を背にしてあと700mのところで下山、つまり生きて帰ってくることを自ら選んだのだ。
「風速何十mという風が吹いていたので、あと30分がんばっていたらまた凍傷になっただろうし、戻ってくることすらできなかったかもしれない。エベレストと対話をして、これ以上は人間が行けない世界なんだと、その境界線のところで戻ってくることができた。以前はそれができませんでした」
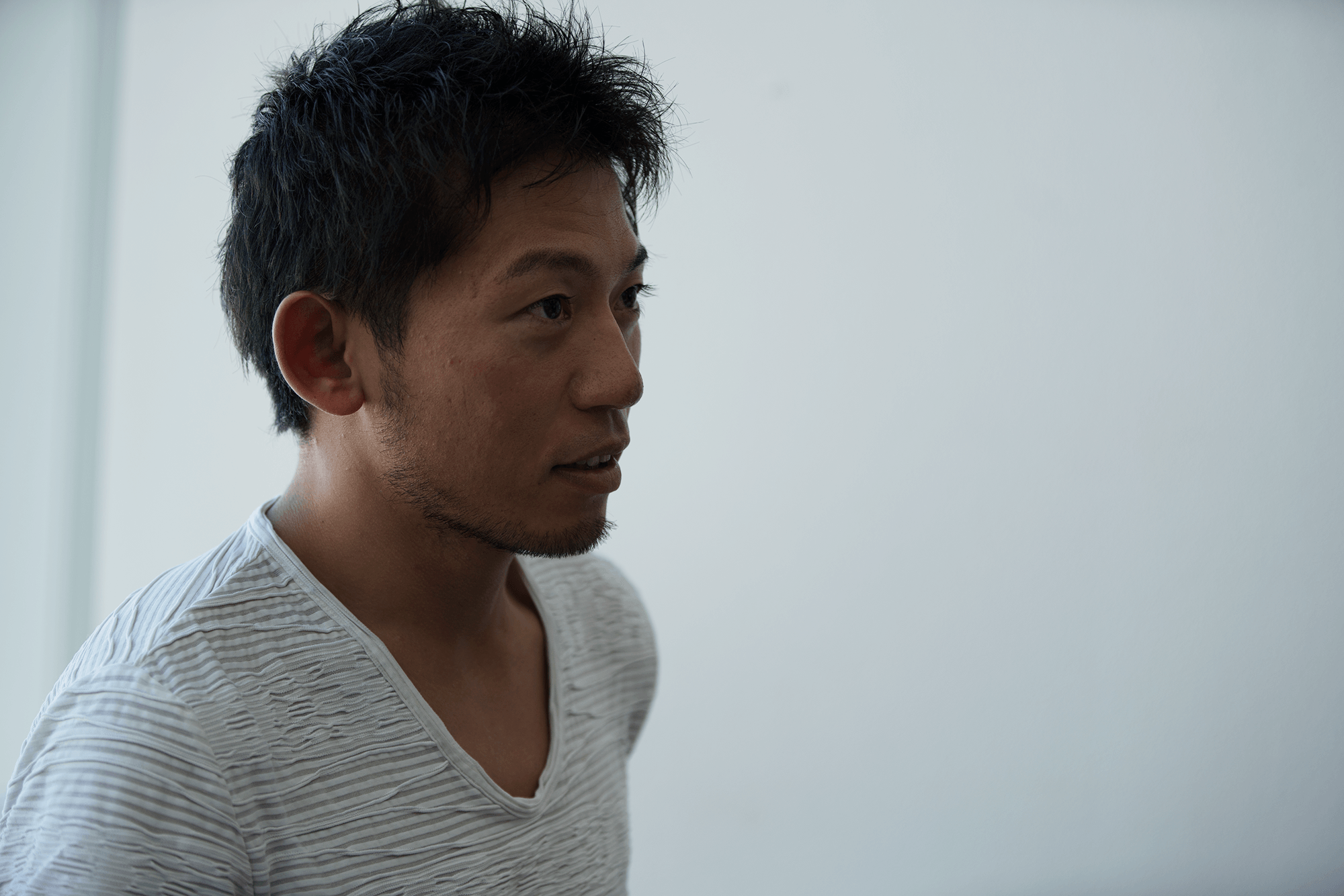
登山家 栗城史多
山と向き合えないことに苦しみ続けた3年間
4度目までの挑戦は山とちゃんと向き合うことができなかった、と栗城は振り返る。
「それまでのエベレストは、ベースキャンプの時点で登れないような状態でした。本当はやめるべきだった。エベレストのような極限の世界は、120%万全を尽くしても何が起こるかわからないくらい。まっさらな状態で向かえるのがベストなんですが、いつも見えない重荷を背負っている感じでしたね」
エベレストを登るルートは、6400m地点から始まる中国側と、5300mから始まるネパール側がある。2009年秋、登りやすい中国側からアタックを試みた栗城は、中国政府から政治的な理由で登山期間を短縮された。それ以来、ネパール側から挑戦を続けているが、2010年は、ベースキャンプに向かう飛行機が悪天候で墜落。そこに乗っていた仲間の一人が帰らぬ人となった。2011年はベテランの山岳カメラマンがベースキャンプに着いて3日後に、くも膜下出血で突然倒れて亡くなってしまった。栗城は精神的なダメージを受けた状態で山に向かわざるを得なかった。
そして迎えた2012年秋、4度目の挑戦。それまでのような外的要因はなかったものの、栗城の精神状態はベストではなかった。
「ちょっと鬱っぽくなっていたんです。眠れない日が続いていて。3年間よくない状態が続いたので、恐怖や不安があったのかもしれません。山と向き合えないことが辛かったんです。精神状態はよくなかったんですが、2012年はそれまでのような外的要因はなかった。だから、風が強くなっていたことがわかっていたのに、欲が出て、ぎりぎりまでがんばっちゃった。もっと早めに下山すればよかったんですが。それが原因で重度の凍傷になり、指を失ってしまいました」

エベレスト4度目の挑戦
山に登れなくなるという恐怖と戦った3年間
秋季エベレスト単独・無酸素登頂、4度目の失敗。重度の凍傷で両手9本の指は壊死。2012年、栗城はどん底の状態に陥った。そこから1年間、指を切断せずにすむ治療方法を探し続けた。日本にはじまり、インドやウクライナにも渡った。それでも結局、切断が一番現実的な方法だという結論に至るだけだった。
「指を失った状態でエベレストになんて登れるわけがない」という周囲の否定の壁。インターネットからも罵声が聞こえる。何より栗城を苦しませたのは「もう山に登れないんじゃないか」と目標を失うことに対する恐怖だった。
恐怖で眠れない日々が続き、栗城の心は病んでいく。異変に気づいた周囲の人に勧められて心療内科を訪れ、医師から薬を渡された。それが栗城にとってはショック療法となり、再び目標に向かわせた。
そして、栗城はアメリカで開発された薬に出会い、再生を促すために、手指9本を切断した。
「指を切断してから3週間くらいはものすごい痛みに苦しみました。基本的に切りっぱなしなので、血がたらたら出る。入院はせず、痛み止めを飲んで耐えていたんですが、夜中も汗をかいて、何度も起きてしまうんです。本当に痛かった。痛みが治まっても、箸も持てない、靴の紐も結べない、お店でおつりももらえない。登山どころか日常生活すらままならない状態でした」
どん底から少し這い上がってきたところでまた栗城の戦いが始まった。
「山には登れても単独は難しいかもしれない、とさすがに思いましたね。一人で山に登るということは全部自分でやらなくちゃいけない。でもそのときの自分は靴の紐も結べずボタンもつけられない。現実はそうでも、自分が求めている山登りの理想を捨てることはできなかった。それでも登りたい、と思いました」
治療のための激痛と思うように指を動かせないもどかしさ。どんなに苦しみが襲っても、栗城はこだわりを持って「エベレストに登る」という自分の夢をあきらめることができなかった。

エベレスト
「2年間、相当しんどかった。エベレストに登るという目標があったから乗り越えられた。目標が見えなくなっていたら、自分はダメになっていたし、失踪していたと思います」
夢を取り戻した栗城は、日々の生活のなかで、山に向けて、マニュアルを作るように自らに課題を設け、一つひとつクリアにしていった。
そして、エベレストに向かうことを決断するための最後の課題に挑んだ。秋季エベレストの事故から約2年後の2014年7月、栗城は再び8000m級の山の世界に戻ってきた。標高8047mのブロードピークを無事登頂したのだ。
「ブロードピークに登れなかったら、正直、エベレストは現実的にもう難しいと思っていました。登頂できたときにまたエベレストの頂上が見えてきましたね」
山に登れなくなるという恐怖に打ち克ち、再び栗城は夢を見た。
苦しみを喜びに、死に対する恐怖を生きる力に変える
絶望の淵にいた栗城を再び山に向かわせ、その道のりを支えた背景に、父の存在があった。
「凍傷になって指を失う可能性があると思ったとき、父に電話をしたら、一言『おめでとう』と言われたんです。『なんでおめでとうなの?』って聞いたら、『一つは生きて還ってこられたこと、もう一つはおまえは苦しみを背負ってまた山に向かうことができる。それは素敵なことだよ』って。当時はすごく辛かったんですが、父のこの言葉がじわじわと響いてきて、苦しみを悲しい体験のままで終わらせないためにもまた山に登ろうと思えたんです」
幼い頃の事故で脊椎に障害を持つ栗城の父は、眼鏡職人になるため東京に行ったり、地元の小さな町で温泉を掘り当てたり、カラオケ施設を作ったり、とにかく挑戦をし続けている。そんな父は栗城に対して「おまえ、苦しんでいるか?」とその背中と言葉で語りかけてきた。
「父は苦しみのなかに学びや成長がある、と思っている人でした。大学時代にマッキンリーへ行くときも、周りの人全員が否定するなか父だけは『お前を信じているよ』と言ってくれたんです。空港に着いた頃に、父がくれた一本の電話、その一言が僕の背中を押してくれました」
苦しみのなかにこそ、学びと成長がある。栗城は父のその教えを山で体感することになる。
「どんな山でも頂上につけば嬉しいというわけではなくて、やっぱりその標高が高ければ高いほど、その途中に苦しみを感じれば感じるほど、頂上に着いたときの喜びは大きい。苦しみと喜びはつながっているんですね」
そうはいっても、その道のりは長い。苦しみが喜びに変わるその瞬間まで、どうやって自分を奮い立たせているのか。
「山を登っている時って、本当に苦しいんですよ。標高が上がれば寒さも眠気も増して、死を意識することだってあります。苦しみって、闘っても勝てないし、逃げても追いかけてくる。でもある時、苦しみは自分自身が作り出しているものだということに気づいたんです。それに同じ状況にあっても苦しいと感じる人とそうでない人がいる。例えばフルマラソンを走っていて、苦しいと思う人もいれば、楽しいと思う人もいて、感じ方は人それぞれですよね。そうなると苦しみは自分でコントロールできるんじゃないか、と。苦しみがあればあるほど、喜びが待っているし、学びと成長がある。そう思って僕は苦しみと“友達”になることを意識しています。ドM人間なので、苦しみがくると嬉しくなっちゃうんですよ」
だからこそ栗城は、エベレストも登山者が多く混雑する春ではなく寒さが増す秋、単独・無酸素という厳しい条件を自分に課す。死に対する恐怖はないのだろうか。
「もちろんありますよ。条件を外して死をかき消すこともできるわけなんです。春に登頂すれば、自分にとって死に対する恐怖は減るでしょう。でも死を意識することによって、生きる力が湧いてくるんです。死というものを人間はどんどん遠ざけようとしているけど、誰にでも必ず死はくる。死んでしまったらだめだけど、僕は山で死を意識するからこそ、生きる力が湧いてくると思っていますね」
死に対する恐怖さえも、生きる力に変える。
「よくやっているね。挑戦を続けているのがすごい」
苦しみを喜びに変え、5度目のエベレストに挑み、生きて帰ってきた栗城に、めったに褒めることのなかった父はそう声をかけた。栗城の挑戦はまだまだ続く。
<後編に続く>
取材・テキスト / 徳瑠里香
写真 / 馬場一萌
栗城史多オフィシャルサイト
http://www.kurikiyama.jp/